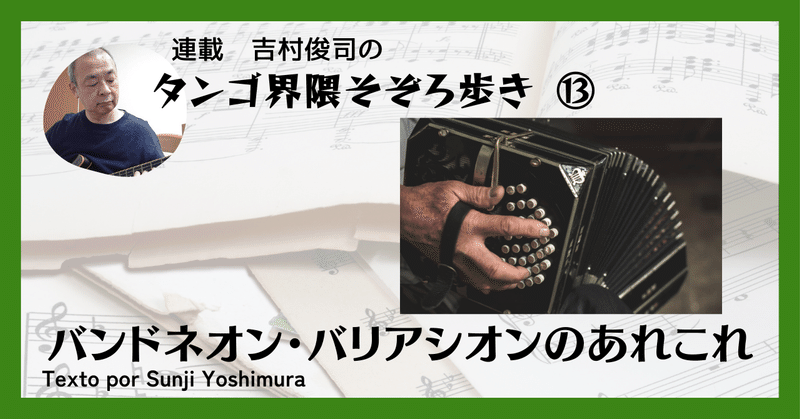
[2024.4]【連載タンゴ界隈そぞろ歩き ⑬】バンドネオン・バリアシオンのあれこれ
文●吉村 俊司 Texto por Shunji Yoshimura
今回取り上げるのはタンゴの演奏の中でも最も華やかな要素の一つ、バンドネオン・バリアシオン。今回も思いつくままにふらふらと歩き回ってみようと思う。
そもそもバリアシオンって何?
タンゴが好きな方にとっては説明など不要かもしれないが、まずは認識をそろえておこう。いろいろ語るより実際に見聞きしていただくのが一番早い、ということで、華麗なバンドネオン・バリアシオンが付いている演奏の定番、アニバル・トロイロ楽団の “Quejas de bandoneón” (バンドネオンの嘆き、作曲:Juan de Dios Filiberto)。せっかくなので映像付きのものを探してみた。1974年の映画のワンシーンで、トロイロが亡くなる前年のもの。
1:45あたりから6人のバンドネオン奏者が一糸乱れぬユニゾンで16分音符の細かいフレーズを弾いている。これがバリアシオンである。
バリアシオンvariaciónは英語のvariationに相当する言葉で、「変化」「変動」そして音楽用語の「変奏」を意味する。変奏とは辞書によれば
へん‐そう【変奏】
〘名〙 楽曲の一つの主題に基づいて、その要素を変化させることによって、曲を構成する技法。比喩的にも用いられる。
ということだ。この変奏の技法を用いて作られた楽曲が変奏曲で、一番わかりやすいのがモーツァルトの「きらきら星変奏曲」だろう。
おなじみの「きらきら星」のメロディが様々に変化していくことがお分かりいただけるかと思う。
タンゴにおけるバンドネオン・バリアシオン
タンゴにおけるバンドネオン・バリアシオンは、楽曲の中の一部としてこの変奏の技法を使って書かれた部分のことである。大抵は16分音符もしくはそれ以上の細かい譜割りで書かれた技巧的なパートであり、楽曲の終盤に配置されることが多い。
タンゴにバンドネオンが定着したのが1910年頃。何人かの先駆者たち ―アルトゥーロ・ベルンシュテイン、ミノット・ディ・チコ、ペドロ・マフィア、ペドロ・ラウレンス等― の努力により演奏技術は飛躍的に向上し、1920年代にはバンドネオン・バリアシオンが演奏されるようになる。およそ100年前のことだ。複数のバンドネオンとバイオリン、ピアノ、コントラバスを基本とするオルケスタ・ティピカと呼ばれる楽団編成が一般化したのと同時期でもある。
例えば有名な曲では、作曲者自らがバリアシオンを書いた “Recuerdo”(想い出、作曲:Osvaldo Pugliese、作詞:Eduardo Moreno)が1924年、“Canaro en París”(パリのカナロ、作曲:Alejandro Scarpino、Juan Caldarella)が1925年の作品。バリアシオンそのものをタイトルに据えた “Milonga con variación”(変奏部付きミロンガ、作曲:Francisco Canaro)などという曲もある。ややこしいことにこれ、リズムはミロンガではなくタンゴなのだが。
現代にまでつながるタンゴの基礎を築いたと言われるフリオ・デ・カロの楽団に名手ペドロ・マフィア、ペドロ・ラウレンスがいたのもこの頃(ラウレンスは1925年に加入しマフィアは1926年に脱退しているので、二人が同時にいた期間は短いものだったが)。“La cumparsita”(ラ・クンパルシータ、作曲:Geraldo H. Matos Rodríguez)の有名なバリアシオンがカジェタノ・プグリッシ楽団で録音されたのは1929年。このバリアシオンは現代に至るまで多くの楽団で使われている。
当時、バンドネオンの速いパッセージによるバリアシオンはさぞかし聴衆の喝采を浴びたことかと思う。今日のロック等でのギタリストによる速弾きのソロと同じような感覚で受け止められていたのかもしれない。もっとも近年はギターソロも歓迎されなくなってきたようだが…いやこの話は関係ないか。
カルロス・ディ・サルリの例外
以後、多くの楽団がバンドネオン・バリアシオンを楽曲に取り入れてきた。上述の “Recuerdo” や “Canaro en París” のように作曲者が自らバリアシオンを書くケースもあれば、“La cumparsita” のように後からバリアシオンが付け加えられるケースもあるが、いずれにしてもタンゴの一つの華であった。
しかし、バリアシオンの存在を頑なに拒んだ楽団リーダーもいる。カルロス・ディ・サルリである。彼はその独自の美学から、極力余分な装飾を排したシンプルで力強いタンゴを演奏し、多くのファンを魅了してきた。そのディ・サルリ楽団で唯一バンドネオン・バリアシオンが付加されている曲がある。1953年に録音された “El choclo”(エル・チョクロ、作曲:Ángel Villordo)だ。バリアシオンはバンドネオン奏者のフェデリコ・スコルティカティによって書かれたもので、初めて聴くといきなり普通の拍の感覚では割り切れない音数のパッセージに度肝を抜かれる。相当に難易度の高いものとなっている。
YouTubeにバリアシオンの部分だけを採譜した動画が上がっていたのであわせて紹介する。これを見ると、最初の割り切れない部分は5連符になっていることがわかる(聴いてわかる人には蛇足ながら)。
これだけの技巧を持った名手が、ディ・サルリ楽団では日頃ひたすら鋭いスタッカートで和音を刻み、ゆったりとメロディを奏でることに徹していたということなのだ(他にもレオポルド・フェデリコ、ホセ・リベルテ―ラ、フリアン・プラサといった名手たちもディ・サルリ楽団に在籍していたことがある)。フラストレーションは溜まらなかったのだろうか…いや、おそらくはそれを補って余りある多くのことがディ・サルリ楽団にはあったのだろう。それより、なぜこの曲だけマエストロ・ディ・サルリはバリアシオンを付加することを認めたのだろう。個人的には長年の謎である。
ちなみにこれを書いたスコルティカティは、実は上述のカジェタノ・プグリッシ楽団の "La cumparsita" の録音にも参加している。歴史に残るバンドネオン・バリアシオン2つに関わっていた人物ということになる。
現代タンゴのバリアシオン
ここまで書いてきてふと気がついた。もしかしてピアソラでタンゴを知ってピアソラ以外のタンゴについてはまだあまりなじみのない人は、これまでバンドネオン・バリアシオンをほとんど聴いたことがなかったのではなかろうか。というのも、ピアソラの少なくとも1960年代中盤以降の演奏には、タンゴの典型的なバリアシオンに該当するようなパートは登場しないのだ。バンドネオンを含む各楽器は、もちろん「ソロ」を弾く。しかしそれはこれまで見てきたような、細かい音符が連続して曲を盛り上げるようなタイプのものではない。タンゴの定型に捉われず、自由な感情表現としてのソロである。
とはいえピアソラも、ある時期まではバンドネオン・バリアシオンを曲の中で用いていた。例えば彼が最初に結成したオルケスタ・ティピカで1946年に録音した “El recodo”(曲がり角、作曲:Alejandro Junnissi)では中盤と最後にバンドネオン・バリアシオンが聞かれる。
個人的にはこのバリアシオン、かなり音使いが異様な感じがしているのだがどうだろう(耳も知識も不足しているのでちゃんと分析できないのだが)。
上記のピアソラを含め、これまで見てきたバリアシオンは曲の和声に基づいた分散和音(アルペジオ)をうまく使ったフレーズであるように聞こえる。そう考えると、次の曲のバリアシオンはちょっと異質といえるかもしれない。アニバル・トロイロ楽団による “Responso”(冥福の祈り、作曲:Aníbal Troilo)。短めのバリアシオンが3:35あたりから始まる。
半音進行の続くこのフレーズは、他の曲での華麗さの演出とは異なる印象を与える。作詞家オメロ・マンシへのレクイエムという意味合いを持つこの曲ならではの表現なのだろう。
ピアソラと並ぶ現代タンゴの巨匠エドゥアルド・ロビーラは、タンゴのバンドネオン・バリアシオンを超えてクラシックの変奏曲的なアプローチが随所にみられる。その中ではこの “Monotemático”(モノテマティコ、作曲:Eduardo Rovira)の終盤聞かれるものがタンゴ的なバリアシオンだ。
音源
以上、タンゴのバンドネオン・バリアシオンについてつまみ食い的にいろいろ見てきた。文中登場した曲や、その他の個人的にバンドネオン・バリアシオンがかっこいいと思っている曲をいつものようにプレイリストにまとめたので、ぜひお聴きいただきたい。
(ラティーナ2024年4月)
ここから先は

世界の音楽情報誌「ラティーナ」
「みんな違って、みんないい!」広い世界の多様な音楽を紹介してきた世界の音楽情報誌「ラティーナ」がweb版に生まれ変わります。 あなたの生活…

