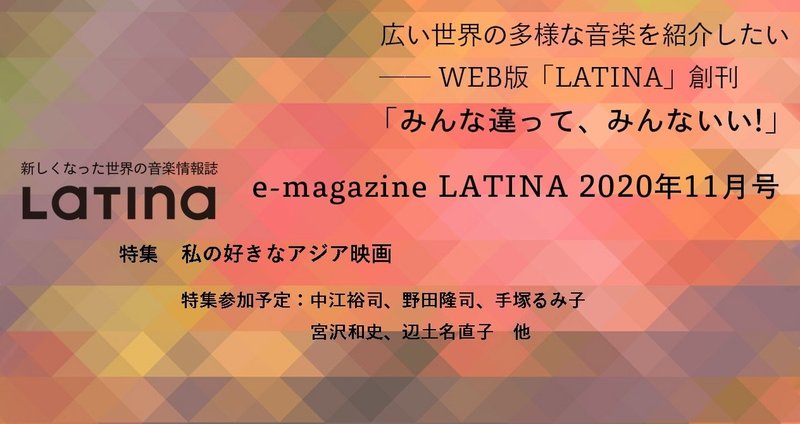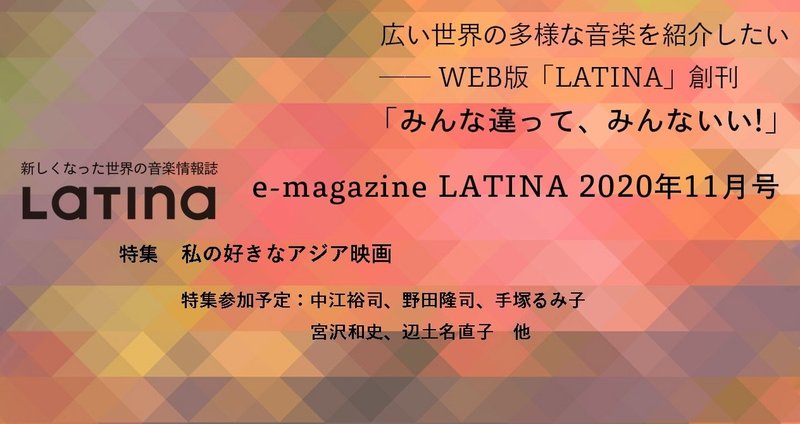[2020.11]【島々百景 第54回】山原(ヤンバル) 沖縄県
文と写真●宮沢和史
2019年10月31日に首里城正殿、北殿、南殿が焼け落ちてから1年が経過した。5度目の再建に向けて集まった寄付金は49億円近くにものぼると聞き、前回の復元から30年近く経って島内はもちろん、全国、いや、世界から愛されるお城であったのだなと改めて実感しているところである。目に見える形としての琉球の尊厳である首里城が焼失した直後の県民の失望感は相当なものであった。彼らの胸中を察するたびにこちらの胸が苦しくなった。“島唄”という歌を作り、沖縄と深く関わるよう