
[2020.12]名盤で聴くウルグアイ音楽(Vol.2)
文●宇戸裕紀
Text By Hironori Uto
ラ・プラタ川。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスとウルグアイの首都モンテビデオを隔てる大きな川だ。日本人の感覚では対岸まで200キロ以上というのは大海だが両都市は同じ川の三角江(エスチュアリー)に位置する。川を一つまたいだくらいで音楽に大した違いはないだろうと思われるかもしれないが、ウルグアイ、アルゼンチンの音楽をごちゃ混ぜで聴いてみよう。「あ、これはきっとウルグアイだ」となんとなくわかることがある。アフリカ移民がラ・プラタ川東岸に残したカンドンベのリズム。70年代〜80年代に特徴的な透明感のある女性ボーカル。ウルグアイ音楽の独壇場ともいえるムルガのコーラス。様々な要素があるのだろうが、モンテビデオの古い街並みを歩いていてまず感じるのが自分の国のことを「Mi Paisito(我が小国)」と呼ぶようにその小ささを自覚しているが故の飾らないかっこよさがある。一国の首都とは思えないモンテビデオ市民の独特のユルさ、誰にも気兼ねなく話しかける市民感覚…小さいが故に成り立つ親しみ深い国民性が音楽にも滲み出ているように思えるのだ。そんな魅力溢れるウルグアイの音楽を俯瞰できるようなグループ、アーティストの作品を50作品ピックアップし、紹介していく(第2回)。

16.Francisco Fattorusoフランシスコ・ファットルーソ/Music Adventure(2013)
現在米国ロサンゼルス在住でファンク、ジャズシーンで活躍するベーシスト。父親はウーゴ・ファットルーソ、母親はマリア・ヂ・ファチマというサラブレッド。ブラジル、ウルグアイ、米国に住んだ経験を持つことから、最も国際的な視野を持ったウルグアイ人アーティストではないだろうか。父、叔父のオスバルドとともにトリオ・ファットルーソとして来日したこともある。レオナルド・アムエドやエルナン・ハシントが参加した『Music Adventure』のこのファンキーさがとにかく刺激的。

17.Gonzalo Levin ゴンサロ・レビン/Arbol
マヌエル・コントレーラ(キーボード)、エルナン・ペイロウ(キーボード)、アントニーノ・レストゥシア(ベース)、フアン・イバラ(ドラム)、ナチョ・マテウ(ベース)らとともにウルグアイ音楽の次世代を担うサックス奏者。ウルグアイ音楽好きなら一度は耳にしたことがある名曲を並べた新作もいいが、今後はもっと踏み込んだオリジナル曲に期待したい。
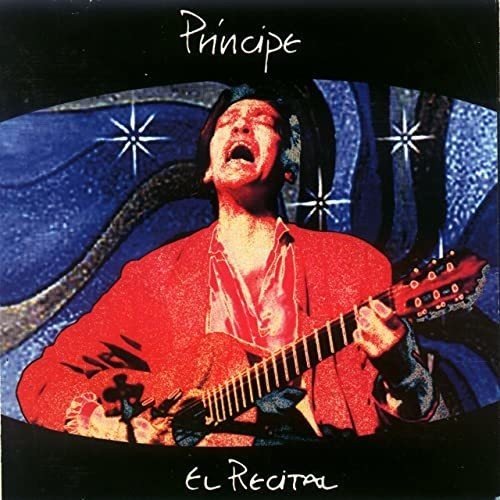
18.Gustavo Pena "El Principe" グスタボ・ペナ(エル・プリンシペ)/El Recital
アルゼンチン人やウルグアイ人のアーティストにウルグアイのおすすめ音楽を教えてというと高い確率でこの人の名前が挙がる。にも関わらず長い間CDもレコードも存在せず、ネット上だけで出回る謎の存在だった。最近になってロリ・モリーナがカバーしたり、共作CD『Fuselaje Púrpura』がリリースされたり、実娘が監督したドキュメンタリー映画『Espíritu Inquieto(不穏な精神)』も2019年に制作され、にわかに日の目を見るようになってきた。2004年に49歳の若さで亡くなったのが惜しまれるが、エドゥアルド・マテオとともに唯一無二の世界観を構築した「エル・プリンシペ」の音楽は、ウルグアイ音楽史の中でも別枠でぽっかりと佇んでいる。

19.Gustavo Ripa グスタボ・リパ/Más Calma
人気の『Calma』シリーズ(これがまた名曲ぞろい)でほとんどギター1本でウルグアイ音楽史を奏でた静寂系ギタリスト。若かりし頃はマウリシオ・ウバルやラウラ・カノウラとともにムルガ〜カンシオンバンド、ルンボの一員でもあった。決して敏腕の早弾きギタリストでなくギター1本でこれほど引き込ませるのは確固たるリズム感とウルグアイ音楽への深い愛情のたまものだろう。落ち葉でいっぱいの冬枯れの山道に差し込んでくる朝日のようなギターの音色に心が温まる。

20.Hugo Fattoruso ウーゴ・ファットルーソ/En Concierto(ライヴ盤)
日本でも最も名が知られているウルグアイ人アーティストは間違いなくウーゴ師匠。ウルグアイ版ビートルズであるロス・シェイカーズとして60年代初頭にアルゼンチン・ウルグアイで一躍名を馳せた。日本で知られるようになったのはなんといってもOPAの革命的なサウンドで、今でも当時の衝撃は語り継がれるほど。70年代以降はエルメート・パスコアール、ミルトン・ナシメント、シコ・ブアルキ、ジャバンのバンドでキーボード奏者としてブラジル音楽へ接近。その過程で知り合ったのが日本におけるラテン・パーカッション界の帝王、ヤヒロトモヒロ(パーカッション)。ご存知の通りドス・オリエンタレスとして毎年来日することになるきっかけとなった。現在ウルグアイでは公私のパートナーであるアルバナ(パーカッション)とのハ・ドゥオでの活動がメインで毎年革新的な作品を日本に届けてくれるのが嬉しい。
*「ファトルーソ」と綴られることもあるが、「t」が二つ重なるイタリア系移民の苗字なので促音表記とした。

21.Jaime Roos ハイメ・ロース/Candombe del 31
団塊世代(?)ミュージシャンのウルグアイ代表はこの人(アルゼンチンはリト・ネビア)。カンドンベ・ロック・ムルガ・ポピュラー音楽の間を変幻自在に動き、その地位を確固たるものにしてきた大スター。一見その辺のおじさん(失礼!)ながらこれほどの人気が高さはわかりにくい高尚な歌詞に頼ることなくモンテビデオの街並みや人を率直に描いた馴染み深いテーマが多いことも関係しているのかも。サッカーウルグアイ代表への思い入れも強く、カンドンベのリズムとムルガのコーラスに代表への想いを乗せた「Cuando Juega Uruguay(ウルグアイが戦う時)」は日本人であっても感極まる。さすが初代W杯優勝国。70年代〜80年代の音源はまるでモンテビデオの街を古びた街角を歩いているかのように鮮やかなイメージが巡ってくる名盤ぞろい。

22.Jorge Drexler ホルヘ・ドレクスレル/Sea
こちらはご存知現代の重鎮。最も来日公演が期待されるウルグアイ人アーティストだろう。現在はスペイン・マドリーを拠点に世界を飛び回り、商業的にもウルグアイ音楽史上最も成功している。ネットでコードが簡単に入手でき、スペイン語圏の若者が気軽にギターの弾き語りができるといういい意味でウルグアイらしくないアプローチのしやすさも成功の理由にあるのだろうか。モンテビデオやブエノスアイレスにはユダヤルーツを持つ人もそれなりにいるが、ドレクスレル家もホルヘの青年期にはイスラエルに1年間滞在している。弟のダニエル、ディエゴもそれぞれミュージシャンで、妻はペドロ・アルモドバル監督『Talk to her』で主演を演じたレオノール・ワトリング(絶世の美女)。近年ではブラジルのカエターノ・ヴェローゾ、メキシコのフリエタ・ベネガス、ナタリア・ラフォルカデとも共演するなど国際性を高め、脂がのっている。

23.Jorge "El Flaco" Barral ホルヘ・"エル・フラコ"・バラル/Chau
同じホルヘだが、こちらは最も知られていないホルヘだろう。インド音楽の影響を受けバンジョー、バンドリン、ギターを弾き語るというさすらいの旅人は現在スペイン在住。2017年にウルグアイの新鋭レーベル、リトルバタフライレコード(Little Butterfly Records)が突如LPをリリース。それ以降一躍時の人に…はなっていない。

24.Jorge Galemire ホルヘ・ガレミレ/Presentación
まるでアルゼンチンとブラジルに挟まれたウルグアイという国の存在そのもののようにどちらかと言えば地味で、名前が全面に出てくる人ではない。それでも70年代〜80年代にかけてロック〜カンシオン〜カンドンベバンドであるエル・シンディカート、ロス・ケ・イバン・カンタンド、レピーケ、フェルナンド・カブレラ、ハイメ・ロースなどの名バンドでクレジットされている縁の下の力持ち。2015年に亡くなるまでモンテビデオのポピュラー音楽シーンで欠かせないミュージシャンだった。

25.Jorge Trasante ホルヘ・トラサンテ/Folklore Afro Uruguayo
アルゼンチンのルーツを音楽家の視点から発掘したのがフォルクローレ研究家で歌手のレダ・バジャダレスだとしたら、ウルグアイ音楽に潜むアフロルーツを打楽器奏者の視点から探求したのがホルヘ・トラサンテ。トラサンテはエドゥアルド・マテオとの共作『マテオ・イ・トラサンテ』でも知られるパーカッショニスト。モンテビデオの中核地区コルドン生まれ(ウーゴ・ファットルーソの自宅も近い)ということもありアフロ・ウルグアイ文化、カーニバルの影響を大きく受けている。1977年から30年間はパリに住み、ジプシー・キングスの一員として演奏したのちウルグアイへ帰国。マテオの音楽にちらりと覗くアフリカ的要素は彼の影響もあるのかもしれない。

26.Jorginho Gularte ジョルジーニョ・グアルテ/La Tambora
母はブラジル黒人奴隷のルーツを持ち、黒き女王と呼ばれたダンサーのマルタ・グラルテ。カーニバルで燃えたぎる血を引き継いだ「ジョルジーニョ」はブラジル南部ポルトアレグレで生まれ、モンテビデオで育つ。70年代からカンドンベ・ビートの中核的人物としてLPをリリースしていたが2002年に謎の暴行事件(未解決)に巻き込まれ昏睡状態となり2013年に息を引き取った。その意志を継ぐべく息子のダミアン・グラルテがSSWとして精力的に活動しているのがせめてもの救い。アフロウルグアイのリズムが炸裂する「タンボール・タンボーラ」はウルグアイ音楽史に光輝く永遠の名曲。

27.Jose Carbajal "El Sabalero" ホルヘ・カルバハル(エル・サバレロ)/Angelitos
「エル・サバレロ(El Sabalero)」*のあだ名もあり、繊維工場で勤務していたという汗の匂いが漂うアーティスト。労働者階級らしくシンプルで飾らないメッセージで人気を博した。アナーキストで、80年代には軍が政権を握ったウルグアイから亡命し、アルゼンチン、スペイン、メキシコ、オランダを彷徨したのち帰国。アルゼンチンのスター歌手、レオナルド・ファビオがカバーした「靴下を5つ丸めてボールにした。昼寝で見た試合では1ゴール差で負けたんだ…」(Chiquillada)や、「酔っ払い、でも花を持って。酔っ払い、でも夢はある」(Borracho pero con flores)という庶民的な歌詞がヒット。モンテビデオの親父たちの叫び声が飛び交うこのライヴ盤でモンテビデオの観客が歌うコーラスも味があっていい。大人の子守唄。
*El Sabalero モンテビデオの西150キロに位置する漁村フアン・L・ラカセの名産がタチウオ(pez sable)であることから由来。

28.Lágrima Rios ラグリマ・リオス/Cantando sueños
「タンゴの黒い真珠」、「カンドンベの淑女」として知られる黒人歌手。グスタボ・サンタオラージャ がプロデュースした『カフェ•デ・ロス・マエストロス』にもウルグアイ人として唯一名を連ねている通りタンゴの世界でも広く知られるが本領が発揮されるのはやはりカンドンベ。渋みのあるヴォーカルがカンドンベにぴったりだ。嘘か誠か、幼少期には近所に住んでいたカルロス・ガルデルに会ったこともあるそうだ。「ムンド・アフロ」のリーダーとして黒人の権利のために活動も行なった。
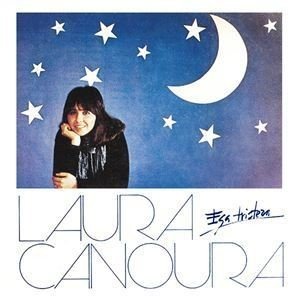
29.Laura Canoura ラウラ・カノウラ/Esa Tristeza
フラビオ・リパ、マリアナ・インゴールド、エステラ・マニョーネとともに清涼感あふれる本格派ヴォーカルで70年代後半〜80年代の女性ボーカルブームの一躍を担った。ピアフのシャンソン曲集(1995年)やタンゴ集(2007年)も残しているが、ハイメ・ロースのプロデュース作ということもあってかウルグアイ感たっぷりの80年代のこの頃が一番脂が乗っていて好きです。
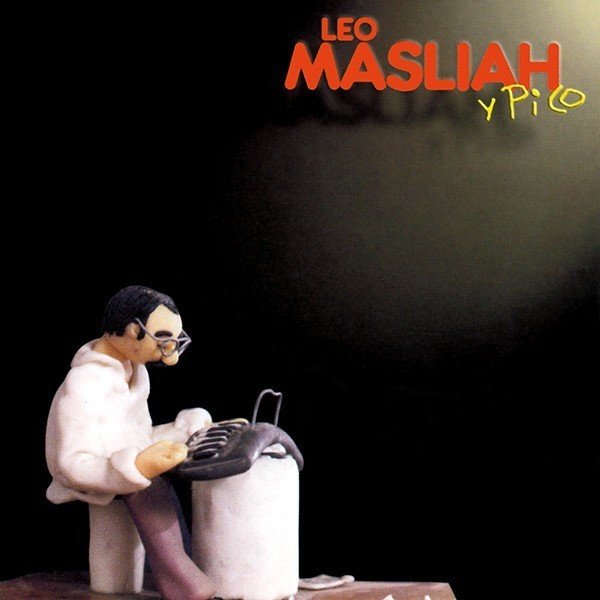
30. Leo Masliah レオ・マスリア/Leo Masliah y pico
短編小説作家やユーモア作家としても知られるピアニストでトルコ系のユダヤルーツ。この人を見ているとさすがフェリスベルト・エルナンデス(ピアニストでもあった)やフアン・カルロス・オネッティといった奇人作家を生み出してきた国だと思う。ミルトン・ナシメントもカバーした代表曲「Birome y Servilleta(ボールペンと紙ナプキン)」では「モンテビデオでは穴という穴から詩人が出てくる…」とアーティストや作家がそこら中を闊歩するモンテビデオの日常風景を温かい眼差しで描写した。楽器を持った若者がそこら中を歩き回る6月18日通り(モンテビデオの目抜き通り)を一度歩いていただければ納得頂けるだろう。ライヴでの一人漫談のような抱腹絶倒MCを楽しみにしている人も多い。このアルバムに収められた「La Tragedia de Ir a Ver Titanic」では映画『タイタニック』を映画館に観に行った際に観客が騒ぎ始めて「うるさい!」「おまえがうるさい!」…と収拾がつかなくなるという悲劇をコミカルに描いている。これほどモンテビデオという街の匂いが染み込んだアーティストも珍しい。
(月刊ラティーナ 2020年12月号掲載)
ここから先は

世界の音楽情報誌「ラティーナ」
「みんな違って、みんないい!」広い世界の多様な音楽を紹介してきた世界の音楽情報誌「ラティーナ」がweb版に生まれ変わります。 あなたの生活…

