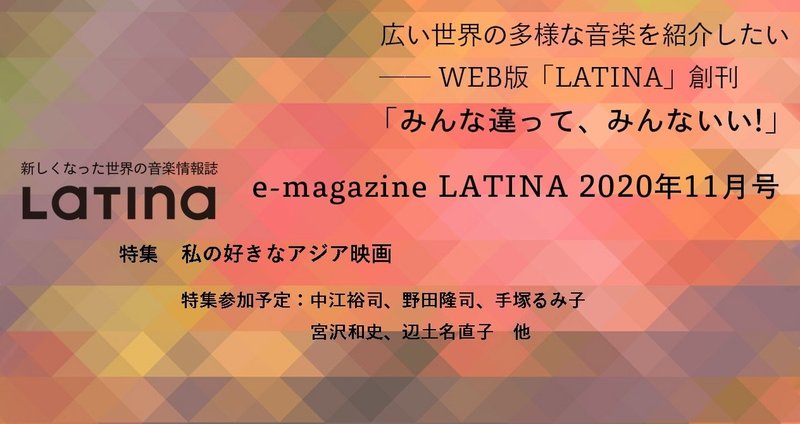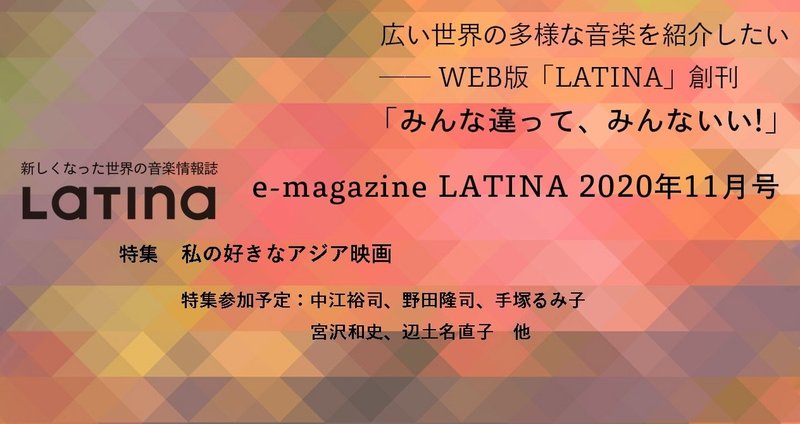[2020.11]中江裕司 【特集 私の好きなアジア映画】
選・文●中江裕司
アジアの逆襲 映画は、フランスで生まれハリウッドで育った。思春期の頃はイタリアのネオリアリズモやフランスのヌーヴェルヴァーグで多感な時期を経て、やはり王道はハリウッドであった。アジアといえば、映画においては辺境でしかない。韓国映画「パラサイト」がアカデミー賞を受賞し、大ヒットしたのはハリウッドの力が弱まっている象徴だろう。「パラサイト」がハリウッド的なのに対して、同じポン・ジュノ監督の「母なる証明」や「殺人の追憶」は、もう二度と撮ることができない気配が漂う